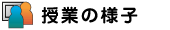 |
9月25日 |
 |
ホンモノパンフレット制作を請け負ってしまった(?)子ども達。その責任の重さをしっかり受け止めている子、今ひとつ実感がわいていない子など、子ども達の受け止め方はさまざまです。
いざパンフレットを作ることになっても、いきなりコンピュータに向かうわけにはいきません。パンフレット作りは、コンピュータ作業までの学習や計画が重要です。今回の取り組みは、かなり長期にわたるものです。その間に、ラフスケッチ(※1)やワークシート、評価カードなどがたくさん増えることが予想されました。それらを保管するためのポートフォリオも作りました。
|
 |
|
授業風景 |
さて、このパンフレット研究は山田教諭の指導のもと、教室で行いました。実を言うと、この子ども達がパンフレット研究をするのはこれが初めてではありません。1学期に三重県のみさきの家パンフレットを作った時にも、家からいろんなパンフレットを持ち寄って研究しました。しかし、子ども達が依頼されたのはコンピュータソフトのパンフレットです。ソフトウェアパンフレットには特有の訴求(※2)手法があります。そこで今回は、ソフトウェアのものに絞ってパンフレット研究するように、担任の山田教諭に依頼しました。教材とするパンフレットは、前日に学校近くのコンピュータショップに行って、たくさんもらってきました。(これもTTの仕事のうちなんです…。)教材がただで手に入るというのは、授業をする上で好都合でした。
 |
|
| パンフレットを研究する子どもたち |
|
授業ではまずはじめにパンフレット用語をおぼえました。キャッチコピー以外にもボディコピー(※3)、キャプション(※4)などパンフレット特有の説明文があることを学びました。それから、子ども達はいろんなソフトウェアのパンフレットを広げて、観察しはじめました。気がついたことは、ワークシートに記入していきます。
|