ワークショップ概要説明
最初に、講師からデジタルレポート制作ワークショップの概要を説明します。ワークショップのねらいや流れ、デジタルで作品を作るメリットなどを解説します。
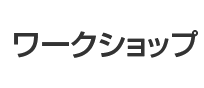

教育の実践研究と普及を行う産学の協同プロジェクトD-projectは、活動の柱のひとつとして、全国各地でワークショップを開催しています。
子どもの学びを見すえた明確なテーマのもと情報教育を実践している現場の教師が講師となって、参加される先生方に生徒の視点で授業を体験していただく取り組みです。
パンフレット作りやCM研究、ホームページ作りなど実際の授業を疑似体験しながら、「メディア創造力」育成についても理解を深める内容となっています。
デジタルメディアに振り回されることなく、子どもの学びを見つめた授業をデザインします。使い方は、その中で自然に学んでいきます。
どんな力がつくのか?どこが面白いのか?どこでつまずきやすいのか?先生自身が体験し、まとめの議論を通じて評価していただけます。
楽しくなければ身に付きません。参加して良かったと思うことうけあい!
作品作りは、2〜3人1組のグループワークで進めます。子どもの立場で協同的に問題解決する学習スタイルを体験していただきます。
最初に、講師からデジタルレポート制作ワークショップの概要を説明します。ワークショップのねらいや流れ、デジタルで作品を作るメリットなどを解説します。
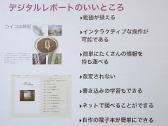
ワークショップの設定は、さまざまな仕事について調べたことをレポートにまとめて人に伝えるというものです。作品作りは、2〜3人1組のグループワークで進めます。子どもの立場で協同的に問題解決する学習スタイルを体験していただきます。

グループで、どの画像・映像を使用するか、説明文はどのようなものにするか、レポートの割り付けはどうするかなど、具体的な内容について検討します。映像と言語を往復しながら、相手や目的に応じて表現する力(=メディア創造力)の育成プロセスが体験できます。

作品はタブレット端末で作ります。レポート作りに使える画像や映像は、あらかじめタブレット端末の中に入っています。画像・映像の撮影や閲覧、インターネット検索、レポート編集などの作業が1台でできるメリットを生かした編集作業となります。

指でタッチするだけで、スライドが変わったり、映像が動き出したり、文字が現れたりといったインタラクティブなデジタルレポート作品の完成です。完成作品は、受講者全員で交流します。付箋紙にその作品のよさ、または改善点などを貼り付けていきます(相互評価)。それを見て、自分達の制作物を振り返ります(自己評価)。

最後に、講師よりワークショップのまとめを行います。デジタルレポート作りの学びの要素、教師の配慮点、伝える作品作りにおける相手意識や目的意識などを解説します。

D-project事務局:〒261-8586千葉市美浜区若葉2-11 放送大学 ICT活用・遠隔教育センター 中川研究室内
TEL:043-298-3401
E-mail:project@d-project.jp
| ▶寺子屋リーフレット制作 | 「カンボジアに寺子屋を!!」本物リーフレット制作 |
|---|---|
| ▶特別支援アラカルト | 特別支援教育でICTの活用場面と方法の具体を提案 |
| ▶国際協働学習の設計と評価 | 国際協働学習のノウハウ、実践を踏まえて |
| ▶AIと教育 | OpenAI ChatGPTやGoogle Gemini、Microsoft Copilot等のAI活用の教育実践研究 |
| ▶STEAMキッズプロジェクト | 教室を飛び出し、ものづくりを通した問題解決力 |
| ▶算数・数学とプログラミング的思考 | Mathpubでプログラミングライクと数学の考え方を同時育成 |
| ▶データベース活用プロジェクト | 調べ学習からデータベース活用の新たな価値を見出す |
| ▶フォトポエム | 写真と言葉を組み合わせ、表現することの楽しさを |
| ▶Everyone Can Create | クリエイティブな表現をとりいれた授業づくり |
| ▶小学校英語メディア創造力 | 楽しく面白く身に付く小学校外国語での効果的な活用 |
| ▶School XR | 空間表現や奥行き感のある表現を生かした活動へ |
| ▶3Dプリンタを活用したまちおこし協力隊 | 学校間交流による地域の魅力を伝える |
| ▶マメ記者プロジェクト・準備会 | 新聞活用で社会にひらかれた学びの実現 |